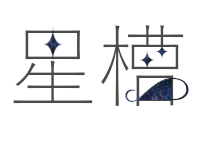▽▲▽▲
業務の合間で医務室へと足を運ぶ。海底の国で最も信頼のおける存在のうちのひとりは、リオセスリが医務室の階段を下りるよりも先に顔をあげて「公爵!」要塞のなかを照らすような明るい声を跳ねさせた。シグウィンの言葉に、ベッドで横になっていた囚人たちが慌てて身を起こそうとする。「ああ、無理して起きなくていい。医務室ってのは、休むための場所だろう?」彼らを言葉ひとつで制してから、リオセスリはシグウィンに迎え入れられた。
「様子はどうだ?」
「いまはもう大丈夫よ、病気に罹ったみんなの様態もずいぶん落ち着いたわ。公爵がすぐ全員に診察の手配をして、薬を用意してくれたお陰ね」
「それが俺の仕事だからな」
シグウィンの言葉に息を吐き、備えつけのものに加えて急遽増設された簡易ベッドまで目を向ける。メロピデ要塞は通気性に欠けた巨大な密室だ、どれほど気を配っていようとも疫病から完全に逃れることは難しい。ひと月の間でメロピデ要塞内は悪性の伝染病に襲われたが、シグウィンの初動が速かったこともあり、流行と被害は最小限で済んだ。
戦場と化していた医務室もいまは落ち着いた様子で、タオルや吐瀉物を受け止めるための容器も散乱していない。看護師たちの間にも、椅子に腰を下ろして息吐ける程度の余裕がようやく生まれつつあるようだった。
「応援は必要そうか、看護師長」
「それなら、夜に何人かお手伝いをしてもらえないかしら。みんなの身体を拭いてあげたり、あとタオルを片づけたりもしないといけないから」
「わかった、ならあとで手配しよう」
伝染病の根絶まで確認出来たら、シグウィンを始めとした医療スタッフには少し長めの休養が必要だろう。大まかなスケジュール調整の算段を立てながら、なんの気もなしにシグウィンの机上で積みあがった本を幾つか手に取る。「ちなみに、これは借りても?」「ええ、いいわよ。そこにある本は全部読んだもの」リオセスリがシグウィンからの快諾と二冊の本を手に収めると、透き通った真っ赤な瞳が無遠慮なほどまっすぐ向けられた。
「ところで公爵、あなたもちゃんと休まなきゃ駄目よ」
「ああ、お気遣い痛み入る。今日はゆっくり読書にでも勤しむさ」
メリュジーヌ特有の視覚は、人間のそれから得られる情報を遥かに上回っている。加えてシグウィンは仕事熱心な人物だ、他のメリュジーヌに比べても人間の感情の機微に一層敏い。幸か不幸か、リオセスリの微弱な変化は要塞内に押し寄せたトラブルに起因していると判断されたらしい。無論それも事実であったから、彼はシグウィンの厚意を受け取るかたちで医務室をあとにした。彼女は聡く鋭い、あまり長居をしては内側にも目を留められてしまう。
そうして執務室へ戻ったリオセスリは、既に片付いた書類を執務机の脇へまとめると椅子を引きながら息を吐く。気を休められる余暇が生まれれば、思考は否応なく水上の夜へ縫い留められた。
――俺と来ないか、と。
差しだした提案に頷かれるとは最初から思っていなかった、そうされるにはあまりにも唐突な発言だ。抽象的な提案は誘い水に過ぎず、水面を震わせるための小石だった。それを受けて滲んだ感情から、彼女を引き入れようと思っていた。
けれど彼女、セヴリーヌはリオセスリの想定から大きく外れ値に飛んだ。驚き戸惑われるどころか、よもや他人からの当たり障りない社交辞令や慰めのように受け流されるとは思ってもみなかった。そうして微笑んだセヴリーヌの内側に揺らぎはなく、水面が波立ったのはリオセスリの胸中。あの夜から、苛立ちに似た思いが腹の底に坐していた。
深く息を吐きながら思考する。ひとつは差しだした手が水鏡に映るものではなく熱を伴った現実であると伝える術、もうひとつは自らの一層内側。想定外の返答、その程度のことに感情が波立つ理由。巡らせ、やがて皮肉めいた笑みが勝手に浮かんだ。結局のところ、すべては我欲に帰結する。
/
リオセスリが収監された頃、メロピデ要塞はこの世のどこよりも凄惨で不毛な国だった。空気以外のなにもかもに金がいる、けれどそれを得るための手段とのレートは狂っている。囚人生活が長く狡猾な者が金をせしめ、またその不平を看守が正すこともない。囚人たちは管理者の横暴に嬲られ、奴隷か玩具のように扱われた。
碌な説明もなくそのような環境へ放り込まれた囚人たちは、まず水と食料を得られない。飢餓に喘ぎながら辛うじて身を粉にしたところで、得られるのはくちびるを湿らせる程度の水ばかり。過酷な生存競争の世界で、そうして弱者は駆逐されていた。
当然ながら、リオセスリも同じ洗礼を受けた。弱者として余分な搾取をされることはなかった、けれど多くを得られもしなかった。真剣と身体の削れる音が内側から響くなか、少しでもそこから逃避するように不衛生な地下通路の隅で目を閉じる。体力の消耗を抑えんと一日の大半をそうして過ごしていたある日の夜、リオセスリの前に誰かが座り込んだのである。
それがリオセスリに危害を加える様子はない。緩慢に顔をあげれば、そこにはひとりの女がいた。自分と同じく、薄汚く清潔さなど無縁の姿。リオセスリよりずっと小さなその女は彼の顔を覗き込むと、手に持っていたものをおもむろにリオセスリへと差しだした。
「はい」
それは、一切れのパンとコップ半分のミルクだった。
「……なんのつもりだ」
この環境において、そして金を稼ぐ術すら悪意によって絞られているなかで、リオセスリにとってそれは高級品にも等しい。それを他人へ差しだす女の意図が理解出来ずに眉を顰めると、彼女はきょとんと目を丸くさせた。
「だって、食べなければ死んじゃうわ」
不思議そうな表情で女は言う。それにリオセスリは愕然とした。
リオセスリは打算を尋ねた。彼女はそれに理由を答えた。女は本気で、その理由で以て、リオセスリへパンとミルクを差しだしたのだ。
「正気か?」
善人を気取った施しとするにはあまりにもささやかだったし、みすぼらしい女の姿からは、あえて善行に走るほどの余裕があるとも思い難い。だがそうでなければ、気が触れているとしか思えない。その精神状態を疑うリオセスリにも、女は不思議そうに首をかしげるばかりであった。
「食べたほうがいいわ。死んじゃったら、そんなの、悲しいじゃない」
彼女はやがて不安そうに眉を下げると、リオセスリの手にパンを握らせようとする。そうして腰が浮かされたところで、女の身体が視界に映った。右膝から下の皮膚に爛れた跡があり、ケロイド状の肌は見るも無残に歪んでいる。工場で働かされている際に薬品か高温に溶けた鉄でもかからなければ生まれない、ひどい火傷の痕跡だった。
こんなにも虐げられ、こんなにも汚されているのに、彼女はリオセスリにパンとミルクを施そうとする。食べなければ死んでしまうから、死んでしまったら悲しいから、そんな理由で。
「…………ああ」
それは、この世界で最も正しいものだと思った。
「そうだな。死んじまうのは、よくないな」
「! ええ、そう!」
それまで自身のなかに存在していた常識が打ち砕かれ、信じていたものは打算と恣意に蹂躙された。だから善悪に唾棄して拳を振るい、両手を命と血に染めた。謳われる倫理を鼻で笑い、美しい正義の内側に汚泥を疑った。
「だから食べて。ミルクに浸して食べるといいわ、そうすると、ちょっと食べやすいの」
だが、猜疑心を飼うこころにとってさえ。女の慈悲は、正しいものだった。正義とは、この女の薄汚れた手であるとすら感じられた。ひびの入ったコップに入ったミルクを受け取ると、女は安堵したように笑う。リオセスリが彼女に言われた通りパンをミルクに浸して食べれば、ほうと深く息を吐かれた。
「……ありがとう。美味かったよ」
「よかった。明日も一緒に食べましょう」
粗末な一切れのパンは、いままで生きてきたなかで最も贅沢な食事だった。リオセスリが女へ礼を告げれば、彼女は嬉しそうに微笑みながらなんてこともなくそう告げる。その声があまりに軽やかだったから、リオセスリのほうが女よりも彼女の無意識を理解してしまった。もしリオセスリが明日もなにもくちにしていなければ、彼女はきっと、なにも考えずに今日と同じことをするのだろう。
「俺はリオセスリ。あんたは?」
「セヴリーヌよ。よろしくね、リオセスリ」
その無垢な善性を正しいと思った、正しさとは地獄で与えられる一切れのパンのかたちをしているのだと知った。
そして正しいものとは、理不尽から守られなければならない。
だからリオセスリは、正なる我欲で以て彼女の救済を望んでいる。