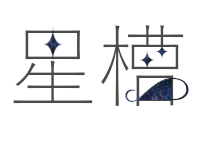2.
異質な生命体との遭遇を果たしてから、アルハイゼンは休日の多くをマウティーマ稠林で過ごすようになった。人間の上半身と魚の下半身を持つ生命体を暫定的に「森海魚」と名称し、その存在の観察と分析に時間を費やす。アルハイゼンにとって未知の生命は、彼を実に喜ばせた。
その休息日もまた雨林の奥地で過ごすため、アルハイゼンは早朝から家を出た。同居人であるカーヴェには「珍しいな」と一言こぼされたが、ただのフィールドワークだと返答すればそれ以上に騒ぎ立てるような詮索もない。理論検証のための実験行動は、学徒にとって論文を読むにも等しい自然行為だからだ。
常日頃と同じように単身で密林へ向かい、水気を多く含んだ草地を踏む。外部刺激に対し燐光を放つ植物を踏み分け、雨林の奥地、僅かに開けた場所に出る。巨大な蛍光植物が傘に溜まった雨水を草地へこぼす水音と、キノコンたちが移動する際にあがる特有の足音。もしくは瞑彩鳥の羽音と鳴き声が僅かに飛び交うばかりの、幽静な土地。アルハイゼンは、そこに異音を吹き込んだ。
指笛を高く鳴らせば、しばらくのちに雨林の空気が一層の水気を帯びる。芳醇な水元素の旋回によって生まれる風元素を推進力として、頭上を滑空する魚の影。陽光が差し込んでなお視認することが可能な巨大茸の燐光、その薄らと色づいたひかりが鱗を反射した。
深緑、薄桃、淡い青。雨林の色に染まってはひかりを弾く鱗が視界に入り、アルハイゼンは自然とその瞳を眇める。森海魚はスメールの色彩を引き連れて、アルハイゼンの眼前へと舞い降りた。
「あぅあ!」
「アルハイゼン、だ」
「あー、う、あ、いぇ」
「ああ」
森海魚はアルハイゼンの名を正しく認識し、その発声を試みる。成果は拙いものだったが人語の発音に必要な舌の動きに成長がみられているため及第点とし、アルハイゼンは首肯することで返答する。森海魚はそれに笑顔を浮かべ、長い尾鰭を揺らめかせた。
それこそが、アルハイゼンを喜ばせる理由。この生き物は既に肉体的な成熟を迎えていながらも、殊コミュニケーションという側面においては最成長期の如き変化を見せているのだ。生命体の飛躍的な発達は特に興味深く、その観察のためアルハイゼンは森海魚へ積極的な交流を図っていた。
「いいか、他者と出会った際には挨拶が必要だ。「こんにちは」」
「ぉん、ぃいぁ」
アルハイゼンが自身の唇を指差しながら発音すれば、森海魚はそれを模倣する。アルハイゼンが頷けば、彼女は破顔とともに尾鰭を揺らす。それは、森海魚が意思疎通の可能な知的生命体であることを示唆していた。
指笛はアルハイゼン来訪の合図だと、唇を指差す動きのときは音の模倣をする瞬間だと認識し、それに応じた行動を取る。それは刺激に対する生理的な反応ではなく、認識と理解という、もう一段階高次の現象が彼女の内側で発生している。アルハイゼンの首肯に対する破顔もそうだ、彼女はそのリアクションが好意的な行為であると認識したうえで自発的に感情を発露していた。
遭遇した当初に取った行動よりも有意味な動きは、彼女の知性が赤子程度には成長したことを示している。肉体、すなわち脳も発達の成熟を迎えているにも関わらず。
「さあ、授業の時間だ」
アルハイゼンが適当な倒木に腰を下ろすと、森海魚もそれに倣う。中空で水元素を凝縮させると、水の塊のうえに鰭を置いた。まるで人間が椅子へ腰かけるように。
アルハイゼンが手に宿した草元素を宙に広げ、それらのかたちを加工する。テイワット共通語の文字を中空へ並べたところで、森海魚はそれのひとつに指で触れた。
「あ!」
「うん、そうだ」
「いぃ」
「惜しいな。正しくは「ビー」だ」
「うぃい」
文字のかたちと音を合致させながら発音を訓練する、ごく単純な児戯。だがその遊戯に耽る森海魚の元素反応を探れば、彼女の体内では水元素が活性化している。下半身が魚であることと関連しているのだろう、森海魚は水元素の操作に長けていた。
空の滑空は風元素ではなく水元素の活性化によって生じた風を用いた動きであり、生命維持に必要な栄養素も主には元素で賄われている。厳密に述べるのであれば、彼女は茸や果実といったものを経口摂取したのちにそれらを一度水元素へ変換し、更にその水元素を必要な栄養素へ再変換することで人間部の皮膚や角質維持を可能としていた。
いまもそうだ、脳の成長は疾うに完成しているにも関わらず彼女の内側は幼児の如く変化している。水元素が脳を直接刺激することで神経細胞を活性化させ、外部刺激を情報として吸収しているのだ。
その水元素の優れた操作性から判断するならば、彼女は元素生命体の亜種だろう。だが水元素を操作した結果として人間部の維持と活性化を行い、果てに肉体の統率部である脳機能を高めていることを考慮に入れれば、彼女はむしろ人間の亜種となる。
「よし、じゃあこれを続けて読んでみよう」
「えぅ、ゆー、えん、いぃ、あぅ、う」
「正解だ。だがこれらがひとつの意味を作るとき、発音は変化する」
現在の生物分類において、森海魚はどこにも当てはまらない生命体だ。前者であれば自然発生した新種の生命体となるが、後者ならばそれは禁忌の遺児になる。それはこの国において、万物に勝る罪悪だった。
「これは、「スメール」と読む」
「うえ、う」
「もう一度。「スメール」」
「うえー、ぅ」
「ああ、そうだ」
推論を重ねながら、世界の根幹を読み解きながら、アルハイゼンは森海魚に言葉を与え、人間とのコミュニケーション・ツールを育ててゆく。
理論と実践の両立によって世界を構築する直線は認識可能になるものの、理解の真髄に至ったことに満足し思考停止していては、そこに累積する知識ほど無駄なものもない。至った理解を前提に、それらをどう用いるか。そこまで思考し、知識は初めて知恵として結実する。
だからアルハイゼンは、森海魚への実験と観察を繰り返す。未知の生命体への理解を深めることで充足される欲求のために、そして満たした欲の先で展開されるだろう事象のために。