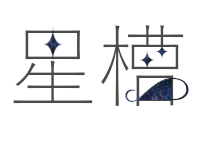まるで獣めいた人間の咆哮、咆哮の如き鬨の声。最前線でそれを煽る身でありながら、意識の奥底が戦争に必要なものを冷たく嗤う。言い知れぬ精神の乖離にも、そこから目を逸らし続ける諦念にも、この五年で疾うに慣れてしまった。慣れなければ、戦争などすることが出来なかった。
頂く王を失い崩れた国は容易く周囲につけ込まれ、砂塵の如く瓦解した祖国の骨格を辛うじて維持し続ける。五年間、そんな戦いに身を投じ続けてきた。父の後を継ぐことは未だ真っ平御免だが、剣を振るう理由から我欲が消えた。帝国の侵略を許さぬファーガス神聖王国としての矜持、領民を守らんとする将の義務。フラウダリウス家が反帝国の立場を示す王侯貴族の旗印となってからは尚更に、極めて個人的な感情に因る刃はフェリクスのなかから失われた。いまの自分を動かしているのは、フェリクス個人の衝動ではない。意地と義心の混ざりあった思いだった。
五年間ともに戦い続けたシルヴァンは、フェリクスを見て「大人になったな」と瞳を眇める。五年のときを経て再会した師は、フェリクスを見て「変わったな」と呟いた。戦のなかで生きるために摩耗された自我を指差されたという点において、彼らの言葉は同義であった。
「援軍を撃破後、各自進軍! フェリクスとアッシュは右翼側へ展開し砲台を押さえろ、シルヴァンは騎馬隊を率いて陽動を。本隊は前進、南方の砦を制圧する!」
咆哮や剣戟のなかにあってすら、件の人物の声は不可思議なほどによく通る。元教師たる指揮官の指示に声があがり、シルヴァンもまた指揮通りに身を翻す。敵が増援を呼ぶ前に各拠点を落とす必要があり、そのうちのひとつはフェリクスに委ねられていた。赤い鎧の兵士を切り伏せ、刃の脂を外套で拭い地に捨てる。血飛沫の散る石畳を踏み進軍を試みた、その瞬間だった。
「っ……!」
殺気が走る。鬨によって昂ぶらされた激情ではなく、汚泥のような怨嗟でもなく。この場においては異質なほどに純度の高い、だからこそ明瞭に感じ取ることが出来た。反射でその場を跳び退けば、フェリクスが踏み込まんとした箇所が矢で射抜かれている。長弓用の矢よりも長く、その鏃は人間の腕で弦を引き放つことも難しいだろう重量。弓砲台から放たれたものであることに相違なく、矢の軌道を遡る。
「――先生」
「なんだ」
「南方の砦は俺が行く」
声は、瞳を動かすのと同時に喉からせりあがっていた。視認するまでもない、肌に刺さる殺気で以て砦の主はわかっていた。作戦変更を進言すれば指揮官たる人物は眉をひそめたものの、三秒後には思考と感情を切り替えるように瞬きをする。三秒の間に悟ったのだろう、フェリクスが意見を変える気はないということに。その判断と決断の速さが、いまはこれ以上ないほどに有難かった。
「シルヴァン、フェリクスに代わって右翼へ展開! 陽動はイングリットが行け! 砦に弓砲台がある、重装兵団から進軍を!」
響く号令、僅かな動揺の伝播、しかし間もなく将が動く。機動力の高さを誇るふたりは愛馬の嘶きとともに地を駆け、空を裂く。一個小隊の隊列が形を変えてなお隙はなく、砦からの増援がアネットの風魔法によって切り裂かれる。彼女に斧を振り下ろさんとした敵の一撃をフェリクスが受け流し、鎧の継ぎ目から内側を削ぐように剣を薙ぐ。刃が骨を削った瞬間に剣を引き、痛みに僅か仰け反った顎の真下へ刃を突き立てた。喉仏から血を噴きだして倒れる兵士から獲物を抜き、血糊を払って剣を構え直す。
「っあ、ありがと、フェリクス」
「かまわん」
アネットの声は哀れみを誘うような震えを帯びている、しかし横目に見た彼女の瞳は恐れるばかりではなかった。当然ながら、戦に身を投じるが故の変化を得たのは自分だけではない。変わらざるを得ないのだ、このような時世とあっては殊更に。
後衛部隊を掩護するように前線へ押し進み、砦への進軍を着実なものとする。剣の一本が脂で使い物にならなくなったから石畳へ投げ捨て、魔法兵団によって無力化された敵の握る剣を引き抜いた。
「先生」
「今度はどうした」
ともに最前線へ立つ人物は、フェリクスの呼びかけに白々しい声を返す。自分の言わんとすることは、砦への進軍を申し出た時点で把握されているのだろう。それでも戦においては確かな意思疎通こそが肝要だ、故にフェリクスは言葉を生む。元教師に「変わったな」と言われるように、幼馴染から「大人になった」と告げられるように。
「あいつは俺がやる。邪魔立てするなよ」
だが、そうして生んだ言葉は戦争において恐らく不要とされるものだ。戦へ身を投じるうちに摩耗せざるを得なかった我欲、軍紀を乱しかねない感情。それをくちにする自分は、かつてに比べれば変わったのかもしれないが、決して大人ではなかった。そうと理解していながら我欲を選択した自分は、復讐に憑りつかれた獣となんら変わりない存在に違いない。
そう自嘲しながらも、言葉の撤回はない。撤回するような意思であれば、元より声にしていない。
「……わかった」
「恩に着る」
あの弓砲台は、間違いなくフェリクスを狙った。本来狙うべきは空駆ける天馬であったろうに、もしくは奇襲に弱い魔法兵団であったろうに。砦へ進軍する本隊への先制攻撃ではなく、北西へ単騎で進まんとするフェリクスをあえて撃ったのだ。それも、ただの一度だけ。他に一切の感情が篭もらない、純然たる殺意だけで。
それがフェリクスに向けられたのならば、自分はそれに答える義務がある。自分だけはそれに応える権利がある。言葉はなくとも確信することが出来た、元より自分たちの間に言葉など必要ではなかったから。
砦への侵攻が開始される。内側の混戦、その合間をすり抜けるようにして階段を駆けあがり砦の屋上へと向かう。鳴り響く怒号と剣戟を踏み潰して鉄の扉を押し開けば、天馬隊の一角を打ち崩した弓砲台の影が揺れた。いっそ冷淡なまで確実に王国軍の戦力を削っていた人物は一匙の未練もなく砲台から離れ、いっそ無防備なまで軽快にフェリクスの前へとその姿を見せる。
「御機嫌よう、フェリクスさん」
「……ああ」
服の端を摘まんだ一礼の優雅さだけは、こんな状況においても変わらない。その異質さに、懐かしさでか、喉が震える。
ロゼッタ=フォン=エーギル。稚き過去に追い求めた、人間の皮を被った獣。その存在はかつてと変わらぬ様子で、至って朗らかな笑みをその顔に浮かべている。