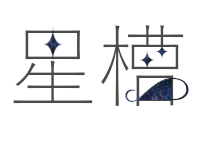ささやかな足音を引き連れて静謐とした廊下を進み、ノックののちに扉を両手で押し開く。教令院の業務の中核を担う空間は冷ややかに澄み渡っており、その洗練された空気は一種の心地好さを孕んでいた。開いた扉の隙間に身を滑らせて、今度は後ろ手にそこを閉める。小さな身体を用いて一連の動作を済ませれば、部屋の主が特徴的な色彩の瞳を僅かに眇めた。
「なにか御用でも」
「大した用ではないわ。でも、あなたにしか聞けないことよ」
「そうでしたか」
ナヒーダの突然の訪問にも、アルハイゼンが動じることはない。表立った変化が想定の最小値に収まる様は、恐らく彼の美点だろう。ナヒーダは書記官の執務室を静かに進む、それを視界の端に留めた彼がくちを開くことはない。沈黙はアルハイゼンから差しだされた敬意だと理解していたから、ナヒーダは有難くそれを受け取った。
「あなたにお願いした件はどうなったかしら、と思って」
「さて、どの件でしょうか」
「大樹になってあげてほしい、とお願いした件。あなたの枝葉が、鳩の止まり木になっていればいいのだけれど」
いまから少し前のことだ。ナヒーダはいまと同じようにアルハイゼンの執務室へと自ら訪れ、彼にひとつの祈りを託した。かつて雨林の民が犯した罪を未だ憎みながらもその中核へ翼をはためかせることを決めた、一羽の鳩。過ぎるほど使命に忠実な姿は、痛ましくも、哀れましくも映った。だからナヒーダは、彼の庇護を決めたのだ。彼もまた、クラクサナリデビが愛するスメールの民なのだから。
雨林の奥地、教令院の内側となれば彼の主人の手も届かない。その彼に代わり、鳩の翼が折られないよう守ること。けれど深く立ち入ることはせず、必要に応じて必要なだけ庇護すること。ナヒーダの祈りを、アルハイゼンは淡々と受け取った。だからその先を知りたくて、彼の執務室にまた訪れたのだ。
「学生から彼に対する不当な要求と発言には注意喚起を行いましたが、それ以外は特になにも」
「あら、本当に? あなたはそのあと、砂漠へ向かったのでしょう。それならあなたも、太陽の織り込まれた翼を見たのではなくて?」
柔らかな問いかけに対する端的な回答は、いかにも彼らしい言葉の選択だ。つまり彼が訪れた砂漠の秘境に関しては、明確にその場を指差されない限りくちを開くつもりもないらしい。
無駄な装飾だと判断した言葉を削ぎ落とす鋭さ、もしくは沈黙という善性。そのどちらもアルハイゼンの魂をかたち取っており、ナヒーダにとってはどちらもが好ましい。でも、どうか今回だけは。扉をノックするように尋ねれば、アルハイゼンは僅かな眉の動きで以て返答とした。
「木々の合間で閉じられた羽、砂海を泳ぐように開かれた翼。そのどちらもを見て、あなたは彼をどのように感じたのかしら」
「別に、どうということもありません。記憶力の優れた人物である、というだけだ」
一羽の鳩――イクリマに対する所見は、やはり彼らしくシンプルなものだった。ナヒーダはそれに首肯で答え、微笑とともに続きを求める。アルハイゼンは今度こそ露骨に眉をしかめてみせたが、ナヒーダが笑みを浮かべ続けることで返事とすれば、彼はそれ以上の反論を諦めたようだった。
「彼の人格は、優れた記憶力を中核として発達したのでしょう。それに加えて閉鎖的で独自の文化が色濃い環境の影響を強く受けた結果として、自我を薄くさせた。あれほど膨大かつ正確な記憶が可能な状態で自我が鮮明になるようであれば、所持する記憶と自我の間での摩擦は免れないでしょうから、妥当な判断とも思われますが」
そうして告げられた見解に、ナヒーダはそっと息を吐く。鷹のように優れた観察眼を持つアルハイゼンであれば、イクリマの記憶力を見抜くだろうことは予想していた。けれど彼の分析はそこに留まらず、イクリマという存在のいびつなかたちさえ捉えている。
彼の知るイクリマという青年は、ナヒーダが庇護を依頼した研究生であり、『沈黙の殿』に所属する烈日の信徒であるというだけの存在だ。だがアルハイゼンはその事実と、実際に見聞きして得た情報だけで、真実へと肉薄した。彼はイクリマが、記録機能を特化させるために自我を犠牲にした存在であることを見抜いている。
「……その彼を見て、あなたはどう思った?」
「別にどうとも。それが原因で教令院内の問題が発生し、彼から救助の要請があるのなら、必要に応じて支援します。だが現状、俺が彼の個人的な問題にまで介入する理由はありません」
「彼の自我が成長することで、あなたひとりでは得られない知恵が実るかもしれないとしても?」
「彼は彼の意思で現状維持を選択している。それが彼から感じた、唯一の我の強さです。そのうえで彼の自我を鮮明にさせることはすなわち、当事者の意思を無視して第三者の意図を強要することになる」
『沈黙の殿』におけるイクリマの役割は秘したまま、ナヒーダはアルハイゼンへ問いかける。そこには一片の好奇心があった、それは人間のこころを紐解かんとするナヒーダの我欲であったかもしれない。けれど多分には、それ以外。ナヒーダの投げたボールを受け止めたアルハイゼンはしかし、それを彼女へ投げ返さず足元へと転がしてしまう。彼はペンを手に取って、問答の閉幕を促した。
「俺は別に、望まない相手を暴いてまで果たす目的を持っていない。それだけのことです」
そうして投げ返されないボールこそが、ナヒーダの最も望んだもの。くちびるから自然と笑みがこぼれ、胸のうちが柔らかなあたたかさに満たされる。ええ、あなたの言う通りだわ。そう頷くと、アルハイゼンは僅かに息吐いた。
彼は聡明な人物だ。蓄えた知識は深く、それらに対する誠実さを失わず、その知見と優れた瞳で以て促されずとも真実へと到達する。そしてそのうえで、彼はどこまでも人道的な判断を下す。ペンとともに告げられた言葉が、なによりもそれを語っていた。
「……やはり、あなたに任せてよかったわ」
「そうでしょうか。彼は俺を蛇蝎の如く警戒していますが」
「あら、それは大変。あなたは安全な大樹だと、彼にわかってもらわなくちゃいけないわね」
だがそれが伝わっていないらしい不幸にナヒーダは眉根を寄せ、思考を緩やかに巡らせる。『沈黙の殿』の若きリーダーとお茶会でもして相談してみようかしらと考えながら、ナヒーダはその身を翻した。これ以上ここへ留まっては、そろそろアルハイゼンに叱られてしまう。
「どうかあなたはそのままで、でも、鳩があなたの枝を止まり木に選ぶように。果実をひとつ、実らせてみるのもいいかもしれないわ」
言葉の間で育む予定にしていた最後の選択肢は彼に委ね、ナヒーダは閉じた扉を両手で開く。彼女を見送る苦い視線に甘い笑みを差しだせば、これ見よがしに深い溜息が扉を閉めた。
書記官の執務室へ置き去りにした言葉は彼を困らせてしまったかもしれないが、きっと問題ないだろう。彼が人道に基づいた善良な人間であることを、ナヒーダは誰よりも知っている。
First appearance .. 2024/09/07
revising .. 2024/11/17