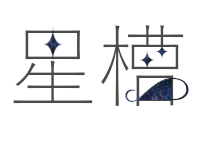「……雨林からの客人、か」
「ああ。『沈黙の殿』の様子を、直接見てみたいそうだよ」
慣れない雨林の手中から慣れた砂海のかいなへ戻った先、そこで告げられた言葉にイクリマはくちびるを閉ざす。その日がやがて訪れるだろうことは理解していたが、迫る事実は彼のなかに容易く馴染もうとしない。ただ、セトスの言葉に対して音のひとつも返さない不敬は許し難いものであったから、そうか、と辛うじて頷いた。
教令院と『沈黙の殿』は共存の道を選択し、互いが持つ知識の共有を受け入れあった。そのためイクリマは自らが望んだ際に知恵の殿堂へ立ち入る権限を与えられたのだが、そもそもそれは交換条件として成り立っている。つまり草神とセノが認めた人物に対しては、『沈黙の殿』の持つ情報を開示しなければならないのだ。
その権限を活用している身であるからこそ、セトスの選択に否を唱えることは出来ない。それでもやはり、教令院の人間へ知識を明け渡すことが恐ろしい。悠久のときを経て存在し続けている『沈黙の殿』は、その存在で以て雨林の裏切りを証明している。自分たちが砂の海へ戻ってそこで暮らし続けている理由を思えばこそ、少なくとも両手を広げて歓迎することは出来なかった。
「客人の道案内はセノが務めてくれるから、僕たちはここで待つだけでいい。ただ、書架の案内は君に頼もうと思ってる。もちろん、つらいようなら他の誰かにやってもらうけど」
「いや、……いいや、おれがするよ。これでも一応、管理者の名を頂いているのだもの」
だが、イクリマ自身の忌避によってセトスの選んだ道を閉ざしてはならない。錆びついた思考を手放すことは出来なくとも、微笑を浮かべることは出来るのだ。気遣わしげに眉をひそめたセトスを安心させるように微笑みながら、イクリマは自らを宥めるように喉元を指で撫でた。
「大丈夫だ、セトス。お前に頂いたお役目は、正しく果たしてみせるよ」
「……うん、ありがとう。頼んだよ、イクリマ」
喉を塞ぐ首飾りの、古い意匠。触れれば指先に滲む金属の冷ややかな感触が、使命と思想の間で喘ぐイクリマの喉に空気を吹き込んでいる。
長く閉ざされ続けていた『沈黙の殿』が部外者のためにそのくちを開く様を、イクリマはいままで数度しか見たことがない。一度目はバムーンの新たな友人としてジュライセンが訪れたとき、二度目は彼を囮にセノたちを招いたとき。そして迎える三度目を、セトスの背後で冷たく捉える。そこに敬慕と忠心の対象が立ってなお、イクリマの意識は張り詰め続けていた。
「出迎え感謝する。紹介しよう、教令院で書記官を務めているアルハイゼンだ」
仲介役を担うこととなったセノの言葉へ、イクリマは静かに一礼をする。その姿は記憶していなくとも、名前と交わした言葉は彼のなかに残っていた。一週間ほど前に知恵の殿堂で出会った、曰く、教令院内においてイクリマの環境保全を担う協力者。この瞬間にようやく、その顔を正しく認識する。
「やあやあ、いらっしゃい。僕はセトス、『沈黙の殿』の首領だ。君のことは、セノやティナリからも聞いてるよ」
「そうか」
社交性に満ちた振舞いで以て歓迎を示すセトスに対して、アルハイゼンの応答はごく端的なものだった。礼を失した態度が主君に向けられ半ば反射的に眉をひそめたが、不敬の糾弾をセトスは望んでいない。イクリマが努めて不快感を堪えている傍で、セトスはおかしそうに喉を鳴らした。
「あははっ、余計な世間話よりも本題に入りたいって顔だ。君の目的は、ここの蔵書の閲覧だったよね?」
「ああ。話が早くて助かる」
「お互いに無理のない範囲で、いい関係を築いていきたいからね。それなら早速、奥に案内しよう」
ひらりと指を動かしてみせたセトスの仕草にアルハイゼンは短く頷き、踵を返した首領のあとを当然のように追っていく。セノがその隣に並び、最後にイクリマが足を動かした。アルハイゼンはセトスが沈黙の殿の内部に関する簡単な案内に頷きながら、神殿の内側を軽い動作で一瞥している。
「……そして、ここがお待ちかねの場所だ。うちはちょっと本が多いから、さっき通ってきた広間や共同区画にもあるけどね」
「成る程。ここと広間の行き来は?」
「自由にしてもらっていいよ。気になる本がどこにあるか知りたかったら、彼に聞いてくれればいい」
道案内の最終地点として並び立つ書架の群れへ到着すると、セトスはイクリマを瞳で招く。最後尾を歩いていたイクリマがそれに応えて足を進め、アルハイゼンの眼前で一礼する。面を上げるとともに見据えた瞳は僅かにその輪郭を歪めたが、その理由をイクリマが探る謂れもない。だからただ、客人を見あげるに留め置いた。
「彼はイクリマ、ここの蔵書はすべて彼が管理しているんだ」
「……ああ」
「それじゃ、案内はこんなところかな。僕とセノはちょっと話があるから席を外すけど、お茶の時間になったら呼びにくるよ。本のこと以外でも、なにかあったときはイクリマに言ってくれたらいい」
「わかった」
親交を深めるという名目で蔵書の閲覧時間に制限を設けたセトスは、イクリマへ目配せをしたのちにセノを連れて書架の合間から去ってゆく。事前に聞いていた話の通りだった。セトスとセノの間には、互いに背負った立場を前提として協議しなければいけないことが山を成している。ふたりの時間はそこに割く必要があったため、アルハイゼンの案内と監視を務める人間が必要だった。そのためイクリマは、主君からの命をひとつ授かったのである。
「お久しぶりです、アルハイゼンさん。なにかありました際には、いつでもご用命ください」
「ああ」
知恵の殿堂で本を読むイクリマに対して、教令院から監視の目は向けられていない。教令院と『沈黙の殿』の立場を対等なものとするのであれば、アルハイゼンを監視する存在は本来不要なものだろう。しかしここには、かつて教令院の犯した罪が根深く残っている。アルハイゼンを値踏みするためにも、そしてこの地に暮らす民の安心を担保するためにも、彼の隣には誰かがついている必要があった。
セトスから与えられた役目を両手で包みながら、早々に書架と向きあい始めたアルハイゼンの傍に控え続ける。アルハイゼンが書架から本を一冊抜き取ればそれを横目で確認し、彼に何事かを問われれば返答するだけの、ごく単純な行為を繰り返す。彼が望む内容が記載された蔵書の有無と、書架に収められている場合はその位置への案内。それはイクリマにとって、食事よりも容易な行為であった。
「……君は、随分と興味深い構造をしているな」
それらを幾度となく繰り返していたさなか、規則的に立ち並ぶ書架の奥深くでアルハイゼンが不意に呟く。彼の目線は高く聳え立つ書架に向けられておらず、また手元の蔵書に落とされてもいない。不可思議な瞳の虹彩は、イクリマへまっすぐに向けられていた。
「そうでしょうか」
「ああ。君は三十人団と親しいようだな、スメールシティではよく彼らとともに行動している。そのお陰で、君の話がよく挙がっているようだ。方向音痴の同胞を、明日は誰が教令院まで連れていくか、だったか」
「……貴方も、三十人団の方とは親しいのですね」
「夜の酒場は、想像以上に声が響く。覚えておいて損はないだろう」
砂漠のさなかで、雨林の記憶を唐突に手繰り寄せられる。一度言葉を交わしただけの存在でしかないアルハイゼンのくちから、彼が知っているはずのない情報を語られる。イクリマが腹を探るまでもなく彼は盗み聞きをあっさりと認めたから、イクリマは自然と瞳を眇めた。
彼に対する知見は少ない、一度しか言葉を交わしていないのだから。だがその一度きりを、イクリマは正確に記憶している。事実の堆積によって構築される言葉が孕む攻撃性、それを理解したうえで出力に躊躇のない暴力性。瞳に警戒を宿しても、アルハイゼンが揺らぐことはない。それどころか、彼はイクリマが鳴らさんとする警鐘すら疾うに想定しているようだった。
「だが不思議なものだ。彼らは君を方向音痴と称したが、それは主に空間把握と俯瞰の問題で起き得るだ。そのためたとえ方向音痴であっても、教令院への道を迷う人間はほとんどいない――どれほど空間把握が苦手であっても、上に向かっていけば必ず教令院へ辿り着くのだから」
ならば君は、どうして教令院までの道を迷うのだろう。問題提起をする声には感情が灯っておらず、淡々としているからこそ皮肉に響く。瞳を眇めるのではなく、明確に彼を睨みつける。アルハイゼンは僅かにその瞳のかたちを変えた。
「考えられる可能性はふたつ、認識と記憶だ。目的地へ続く道がそうであると認識出来ない、もしくはそれが記憶出来ない。……君の様子を見る限り、後者だろうな」
「何故、そう思われたのでしょう」
「知恵の殿堂で君と会ってから今日までの間、俺たちはシティで三度すれ違っている。その際、君が俺を視界に入れても俺に気づくことはなかった。だがその一方で、君は三十人団の傭兵たちを正しく識別している。つまり君が相貌失認の類であるとは考えにくい、その場合はひとの顔全般を認識出来ないはずだからな」
それに、もし君が方向音痴なのだとしたら、この書架の管理など到底不可能なことだと思わないか?
言葉は単調に紡がれる、観察した結果が無感情に積みあげられる。観測内容から推論を導き、イクリマの眼前に突きつけて彼の反応を見ることで仮説の検証を試みている。それはまさしく、実験行為だ。アルハイゼンは、イクリマを対象とした観察研究を行っていた。
「果たして、そうでしょうか」
「ここは方角の認識も難しい閉鎖空間だ。そこで規則正しい光景が連続している場合、それぞれの書架に収蔵されている本の位置を正確に認識するためには、むしろ相当の記憶力と俯瞰能力が求められる。君が本当に方向音痴だとするなら、俺はいまここで、この本を開けていない」
アルハイゼンが開いた本は、イクリマが案内した書架に収まっていたものだ。つまり彼はここで『沈黙の殿』の蔵書を閲覧して門外不出の知識に触れると同時、イクリマに対しても一定の刺激を送っては返される反応を検証していたことになる。
「恐らく君は、特定条件下のものしか記憶することが出来ないのだろう。そのため教令院へ続く単純な道も覚えられない一方で、驚くべき記憶力を発揮する」
その労力を支払ってまで、彼はイクリマを観察している。ただの研究生、ただの砂漠の民でしかないイクリマを。
「十数人に及ぶ第三者の所属学派と研究テーマを正しく記憶することも、これほどの蔵書のなかから特定の情報の有無を判別することも。並大抵の記憶力で出来ることではない」
そして検証を終えたのだろう仮説を片手に、彼の瞳がかたちを変える。今度こそ、明確に。アルハイゼンは、薄らと笑ってみせた。
「ならば、君は。果たしてなにを、どれほど、どこまで記憶しているのだろうな」
無感情だった声と瞳に笑みが混ざる、言葉と顔にアルハイゼンの感情が溶ける。感情とはすなわち意識の方向性であり、彼は積みあげた事実による仮説へ自らの意思を宿したのだ。イクリマという存在を暴かんとする意思を。
「……貴方は、ご自身の職責に因ってこちらへ来られたのでしょうか」
「いいや。俺の個人的な関心だ」
だがイクリマの持つ機能は、『沈黙の殿』が所有するすべての蔵書にも勝る秘匿とされている。当然だ、彼は『沈黙の殿』が持つすべての書物そのものなのだから。
呼吸する記録機能、人間型の古代図書館。イクリマにとってはごく自然な記憶行為でありながらも、膨大な記録の貯蔵が可能な肉体は『沈黙の殿』で保護されている神秘のひとつでもある。
「それであれば、貴方にお話することはなにもありません」
彼の使命と肉体が砂漠の神秘に属する限り、イクリマという存在を暴くことは許されない。それはもはや烈日への冒涜にも等しく、私的な好奇心によって触れてはならないものなのだ。イクリマは自身の喉元に指先で触れながら、アルハイゼンへ微笑を向ける。滑らかな表情の変化を受けてか、彼は僅かに刻んでいた笑みを無音で取り去って瞳を瞬かせた。
「成る程。では、俺が書記官の権限で以て尋ねた場合は?」
「然るべき対応に応じて、然るべき方から、然るべきだけ話されるでしょう」
「もしも、然るべき対応を取らなかったとしたら?」
イクリマが首を左右に振ってなお、アルハイゼンは秘匿の輪郭を探るように言葉を紡いで疑問を重ねる。だがそれは、疑問という体裁を取っているだけの欲望だ。太陽への信仰心なくして、砂漠の神秘が開かれることなどないというのに。
ああ、と。細く嘆息しながら、指の腹で首を撫でる。やはり警戒をほどくべきではない、雨林の人間を砂漠の叡智に触れさせてはならない。たとえ草神の信頼が厚い人物であろうとも、たとえ敬慕の先にいる人物がこころを許した相手であろうとも。
「おれは貴方の目の前で、もの言わぬ存在となるでしょう」
彼は、知欲の化物だ。貪欲なる知識の獣はその嗅覚でイクリマの孕んだ神秘を嗅ぎ分けたのだから、いつ、いかなる手法で以て砂漠の秘匿を食い荒らすかもわかったものではない。
だからイクリマは、自らの指で以て緩やかに頸を絞める。彼は自らの判断で、いつでもそうすることが出来るのだから。
「……そうか。それは残念だ」
「そうですか」
「ああ」
明快な欲望へ、明確な事実を返す。いまはまだ起きていない、けれど彼が知欲の怪物を解き放てば必ず起こる事象を示す。そうすることで彼はようやく好奇心を下げたから、イクリマも一旦は喉元に触れていた指をほどいた。それでも、指先にはまだ、首輪の冷ややかな感触が残っている。
アルハイゼンから、それ以上の追及を受けることはなかった。彼はセトスとセノが書架の合間へ舞い戻るまで『沈黙の殿』の蔵書へ目を通し続け、時間制限を示す休息のあとは神殿内へ腰を下ろすこともなくセノとともに雨林へと戻っていった。
柔らかな砂嵐の合間に溶けてゆくふたりの背を見届け、『沈黙の殿』はくちを閉ざす。青く透き通った石による扉の固定を確認し、セトスはイクリマの手を掬いあげた。
「お疲れ様、イクリマ。彼はどうだった?」
無邪気な振舞いは、強張ったイクリマの身をほぐすための配慮だろう。来客の歓待やセノとの協議を行ったセトスのほうがよほど、慮られて然るべきなのに。彼に余分な気を回させてしまったことへの苦みに一度閉ざしたくちびるは、けれどそのままでもいられない。それが、と呟くと、セトスの顔から穏やかな笑顔が静かに落ちた。
「……首領へ、ご報告がございます」
「……うん。なら、部屋に行こう」
目を伏せたイクリマへ、セトスは浮かべていた笑みと同じほどに穏やかな声を紡ぐ。掬われた手はほどけることもなく、セトスはイクリマの指を柔らかく包み込んでいる。イクリマのものよりも幾分高い体温に、ほんの少しだけ瞳を眇めた。
両目を潰されようとも不自由なく歩くことの出来る空間でも、雨林の街を散策するときのように手を引かれる。そうしてセトスは彼を自室へ招くと、広々とした寝台へ腰を下ろした。イクリマの手首をなぞるようにしてから指がほどかれ、彼はその場に跪く。「ご報告致します」主君への奏上に、うん、と許可を下ろす声。それを以てイクリマは、首を垂れたままにくちを開いた。
「雨林からの客人……アルハイゼンに、おれの中身を気取られました。警告をすれば、一応は引き下がりましたが」
「そう。詳細を教えて」
「承知致しました、二件の記録を再生します。――記録一。十日前、十一時二十六分、知恵の殿堂。話者、イクリマ、アルハイゼン、教令院所属・生論派学生――名称不明。学生、行動。イクリマへ接近。学生、発言……」
記録された内容を一言一句違わずに再生する。記録機能としてのイクリマにとっての記録対象は、文字情報に限らない。自らの五感で得た情報を記録し、そこに一切の恣意を介在させることなく出力する。書架で起きた出来事をすべて音声で以て再生し、出力を終えた身体に僅かな硬直。「……再生を終了します」その言葉を合図とするように、イクリマは細い呼吸をゆっくりと繰り返す。そうすることで記録機能の活用時には不要な意識を自らへと嵌め込んでゆく。閉じていた視界を緩やかに開けば、ブーツを脱ぎ捨てたセトスが寝台で足を組みながらその思考を巡らせていた。
「ふうん……成る程ね」
「……申し訳ありません。おれの発言が軽率であったばかりに」
「いいや、君に落ち度はないよ。彼が優れていただけのことだ。まさかそこまで観察眼が鋭いとはね、教令院の代理賢者を務めていただけのことはある」
イクリマはアルハイゼンが信用に足る人物であるか確認するために、彼の記録していた情報を提示した。だがその行動を取らなければ、アルハイゼンはイクリマが持つ記憶の特異性に気づくことはなかっただろう。
己の失態にくちびるを噛み締めていれば、それを咎めるようにくちもとを撫でられた。セトスの指がイクリマのくちびるに触れたから、それを受け入れるべく寝台のすぐ傍にまで身を寄せる。セトスはイクリマの同じ動きを何度か繰り返すと、その指をやがてほどいた。
「君の警告で追求をやめたんだ、それがただの脅しじゃないって理解したんだろう。彼は草神様も信頼するほど聡明な人物のようだからね」
そしてセトスはその身を倒し、緩やかにイクリマの身体に触れてゆく。くちびるから顎を撫で、喉を辿る。そこは、古い金の飾りがついた首輪に塞がれていた。いままでと変わることなく、これからも変わることなく。
「心配しなくていい、きっと彼はこれ以上の追求をしてこないよ。もし二度目があったとしても、今日と同じように断るだけでいい。それ以上のことがあったときには、迷わず僕のところまでおいで。そうなったとき、対処するべきは僕と草神様になるからね」
だから、と、セトスは呟いた。古い意匠の首輪を撫でられるから、イクリマは首を差しだすように顎を逸らす。それでも喉が露わになることはなく、金属越しに喉の凹凸へと触れられた。
「……だから、イクリマ。決して、これを使っちゃいけないよ」
低い声と冷たい瞳がイクリマへと厳命する。それは『沈黙の殿』の首領が下した判断であったから、イクリマに逆らう理由はない。首を差しだしたまま、イクリマは静かに目を閉じる。
「かしこまりました。首領の仰せのままに」
それはイクリマの命を奪い、砂漠の叡智を守るための装置だ。彼が簒奪者の手に渡った場合、致死性の毒がそこから体内へ注入されるようになっている。知欲の怪物がイクリマに喰らいつくようであれば、装置の起動は当然ながらイクリマの取るべき選択肢として存在していた。
「大丈夫だよ、イクリマ。悪夢は所詮、ただの夢だ。君の恐れていることは、現実にならない」
「……はい、首領」
だが、他ならぬセトスがそれを取りあげてしまったから。イクリマは祈るように両手の指をそっと組む。
否、それは祈りに違いなかった。